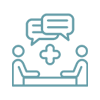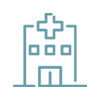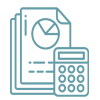「医師の求人を出しても応募がない…」「せっかく採用できてもすぐに辞めてしまう」――そんな悩みを抱えていませんか?医療現場における人材不足は深刻化しており、特に医師の採用・定着は、病院経営を左右する大きな課題となっています。高度な専門性と責任を担う医師という職種においては、給与や待遇だけでなく、働く環境・キャリア支援・職場の文化といった“見えにくい部分”が採用成功の鍵を握っています。
さらに2024年から始まった医師の時間外労働規制により、病院側には「働きやすさ」を具体的に提示する義務が生じるようになりました。つまり、これまで以上に「選ばれる病院」になるための戦略が必要なのです。
本記事では、医療現場の現状を踏まえつつ、医師にとって魅力的なオファーの出し方、採用後に定着してもらうための組織づくり、そして病院経営に役立つデジタル施策や公的支援制度の活用方法までを、わかりやすく解説します。
1.医療業界における人材不足の現状と課題
1-1. 医師・看護師の有効求人倍率と人手不足の実態
日本の医療業界では、医師や看護師を中心とした深刻な人材不足が続いています。厚生労働省の調査によると、看護職の有効求人倍率は常に2倍を超える水準にあり、地域によっては必要な人数の半数にも満たないケースも少なくありません。
特に地方や離島では、専門医や夜間勤務が可能なスタッフの確保が困難であり、都市部との医療格差が拡大しています。こうした現状を放置すれば、医療の質の維持が難しくなり、病院経営にも大きな影響を及ぼします。
1-2. 人材不足が病院経営に及ぼす影響
人材不足は単なる業務負担の増加にとどまらず、病院経営全体に深刻な影響を与える要因となります。
たとえば、医師や看護師が不足することで、外来や入院の受け入れ制限を強いられるケースもあり、診療報酬の減少や収益の悪化に直結します。さらに、スタッフの負担増によるサービス低下や医療ミスのリスク上昇は、患者満足度の低下や評判の悪化にもつながりかねません。
結果として、悪循環が生まれ、優秀な人材がさらに集まりにくくなる状況に陥るのです。
1-3. 離職率の高さとその要因
医療現場の離職率は依然として高く、特に看護師では3年以内の離職率が30%を超えるとも言われています。その要因としては、過重労働・長時間勤務・人間関係のストレス・キャリアの見通しの不透明さなどが挙げられます。
また、近年ではワークライフバランスを重視する若手医療従事者が増えており、過度な夜勤や休日出勤のある勤務体制が敬遠される傾向にあります。
このような環境を見直さなければ、採用活動がうまくいっても定着率が上がらないまま慢性的な人材不足が続いてしまいます。
1-4. 労働環境の問題点と改善の必要性
医療現場の労働環境には、人員の過不足だけでなく、制度や運用上の問題も数多く存在します。たとえば、労働時間の管理が不十分で実質的にサービス残業が常態化している現場や、評価制度が不透明でモチベーションが上がらない職場も少なくありません。
これらの問題を放置すると、従業員の満足度が下がり、結果的に離職やミスの増加を招きます。
そのため、今後は**「働きやすさ」や「キャリアの見える化」を意識した職場環境づくり**が必要です。職場の魅力を高めることは、人材の定着率向上だけでなく、採用競争に勝ち抜くための差別化ポイントにもなります。
2. 効果的な医師採用戦略の立案

医師の採用は、医療機関にとって経営の根幹を支える極めて重要な課題です。しかし、従来型の募集方法では限界があるのが現実。そこで本章では、採用市場の理解をベースに、医師に選ばれるための戦略的アプローチを解説していきます。
2-1. 採用市場の理解と医師にとって魅力的なオファーの提示
医師採用においてまず重要なのが、「市場を知る」ことです。医師は他業種と比べて求人倍率が非常に高く、売り手市場が続いているため、病院側が「選ばれる立場」であるという前提に立つ必要があります。
採用成功の鍵は、医師にとって魅力的なオファーを用意できているかどうか。報酬だけでなく、勤務条件(週何日勤務か、当直の有無)、専門性が活かせる診療体制、将来的なキャリアパス、家族への配慮(転居支援や保育環境など)も重視されます。
医師が「この病院なら長く働けそう」と感じる環境を整備することが、応募につながる第一歩です。
2-2. 採用機会を増やすためのアプローチ方法
良い条件を整えても、それが「届かなければ意味がない」のが採用活動です。現在の医師採用では、単に医師求人サイトに掲載するだけでなく、多面的なアプローチが必要です。
たとえば:
- 医師専門の人材紹介会社との連携:特定の専門医や経験者をピンポイントで紹介してもらえる。
- 学会や研修会でのリクルーティング:自院の魅力を医師自身に直接伝えるチャンス。
- 医学生・研修医との早期接点づくり:将来的な採用に向けて関係構築を図る。
- 病院HPやSNSを活用した採用ブランディング:職場の雰囲気や働くスタッフの声を発信。
また、医師の多くは「紹介」「信頼」「経験」を重視するため、**現職の医師からの紹介制度(リファラル採用)**も効果的です。
2-3. 採用成功事例の紹介と分析
実際に成果を上げた医師採用の事例から学ぶことは多くあります。ここでは2つのタイプの成功事例を簡単にご紹介します。
■ 地域密着型クリニックの事例
地方都市の診療所では、都市部からの医師採用に苦戦していましたが、「週3日勤務+高収入+学会参加支援」という柔軟な勤務条件を打ち出した結果、家庭との両立を望む30代の医師の採用に成功。さらにその医師の紹介で2名の医師が続いて採用される流れに。
■ 中規模病院のMEO活用事例
別の病院では、Googleビジネスプロフィールの運用を強化し、「医師 求人 ○○市」での検索結果に上位表示されるよう対策。結果として、自院のWebサイト経由での問い合わせが2倍以上に増加しました。
このように、医師のライフスタイルに寄り添った提案や、Web上での露出強化が採用成果に直結することが分かります。
3. 働き方改革と労働環境の整備
医師の確保と定着を成功させるには、魅力的な求人条件を提示するだけでは不十分です。働きやすい職場づくり=定着率向上と医療の質の維持に直結します。本章では、制度対応から実践的な職場改革まで、医師の働き方を見直すための具体的な取り組みを紹介します。
3-1. 医師の時間外労働の上限規制とその対応策
2024年4月から「医師の働き方改革」が本格施行され、**医師にも時間外労働の上限規制(原則年間960時間、例外でも1860時間)**が導入されます。
これは単なる制度変更にとどまらず、病院の診療体制や人材配置の見直しを迫る大きな転換点です。
■ 対応のポイント
- 当直・オンコール体制の見直し:複数の医師で分担し、特定医師への過剰負担を防ぐ。
- タスクシフティングの推進:医師が行っていた事務業務・説明業務を、専任スタッフ(医療秘書や看護補助)に移譲。
- 診療スケジュールの効率化:予約制の徹底や再診枠の調整で、医師の拘束時間を短縮。
この規制は「制約」ではなく、働き方を見直す好機と捉えるべきです。
3-2. ワークライフバランスを考慮した勤務体制の構築
今や、医師も「働き方を選べる時代」。特に若手医師や子育て世代にとって、収入よりも柔軟な勤務条件やプライベートの充実が重視される傾向にあります。
■ 取り組むべき勤務体制の工夫
- 週4日勤務・時短勤務・当直なしの選択肢を提示
- シフト希望の柔軟対応(家族の行事や学会との両立ができる環境づくり)
- リモートによるカンファレンス参加や文書業務の一部在宅化
病院にとっては一見「負担」ですが、これらの配慮が医師の応募動機や定着理由につながります。長く働いてもらうには、「この病院なら自分らしい働き方ができる」と思ってもらえることがカギになります。
3-3. 労働環境改善による離職率低下の取り組み
労働環境の整備は、採用後の定着率を左右する最重要ファクターです。医師が辞める理由の多くは、給与よりも「人間関係のストレス」「過重労働」「評価制度の不透明さ」にあります。
■ 離職を防ぐ職場づくりのポイント
- 定期的な面談・フィードバック制度の導入:医師の不満や希望を早期にキャッチ。
- 明確な評価基準と昇進制度の整備:努力が正当に認められる環境をつくる。
- 医療安全やクレーム対応の体制強化:医師が安心して診療に集中できるようバックアップ。
小さな取り組みの積み重ねが、医師が「ここでずっと働きたい」と思える病院文化の醸成につながります。

4. 人材定着のための組織戦略
医療現場では採用活動以上に、「定着率の向上」が喫緊の課題です。優秀な人材をいかに離職させず、モチベーション高く働き続けてもらうか。それには給与や待遇以上に、働く環境と組織文化が大きく影響します。本章では、人材が根付きやすい職場づくりの具体策を紹介します。
4-1. 職員の価値観を尊重した労働環境づくり
定着率の高い病院に共通しているのは、「一人ひとりの価値観を理解し、活かしている」ことです。医師やスタッフはそれぞれ、働く目的や大切にしている価値観が異なります。
たとえば、「専門性を高めたい人」「子育てと両立したい人」「地域貢献を重視する人」など、その背景はさまざま。これを理解せずに一律の働き方を押しつけると、ミスマッチが生じ、離職につながってしまいます。
■ 実践のポイント
- 面談やアンケートを活用し、スタッフの希望や悩みを把握
- 価値観に合った配属・働き方の提案(例:救急が得意な医師には救急外来中心のシフト)
- 個々の目標や意欲に合わせた評価や支援の仕組みを整備
「この病院は自分のことをちゃんと見てくれている」――そう感じてもらえる職場は、定着率も自然と高くなります。
4-2. キャリアアップ支援と教育体制の充実
人が長く働きたいと感じる職場には、「成長の実感」があります。医師も看護師も、「学び続けられる環境」があるかどうかを非常に重視しています。
■ 病院が取り組むべき育成支援
- 学会・研修参加の積極的な支援(出張費補助や勤務調整など)
- 院内での定期的な勉強会・症例検討会の開催
- eラーニングや外部講師を活用した学習機会の提供
また、専門医資格取得を目指す医師には、症例数の確保や指導医の配置などの支援があると非常に魅力的です。
教育のある病院は、「自分を高められる場」として選ばれ、そして残ってくれる人材も増えます。
4-3. メンタルヘルス対策と職場のサポート体制
忙しい医療現場では、心身の不調に悩む医療従事者も少なくありません。**メンタルヘルスのケアは、今や病院経営における「攻めのリスク管理」**とも言えます。
■ 実効性のあるサポート体制の例
- 定期的なストレスチェックと相談体制の整備(産業医・カウンセラーの設置)
- 休暇取得の促進とリフレッシュ休制度の導入
- 「困ったときに頼れる」相談窓口やピアサポート制度の設置
また、管理職やチームリーダーに対しても、**マネジメント研修(傾聴・フィードバック・感情労働への対応など)**を実施することで、現場でのトラブルや摩擦の予防につながります。
5. 採用活動におけるデジタルツールの活用
医師の採用競争が激化するなかで、従来の紙媒体や紹介だけではアプローチが届きづらくなっています。現代の採用活動では、デジタルツールを駆使して「知ってもらい、興味を持ってもらう」ことがカギです。本章では、ウェブサイト・SNS・オンラインイベントを活用した実践的な採用戦略をご紹介します。
5-1. 病院ウェブサイトの採用ページ最適化
医師や医療スタッフが求人を探す際、まずチェックするのが「病院の公式サイト」です。ところが、採用ページが形式的だったり情報が少なかったりすると、それだけで応募意欲が下がってしまうことも。
■ 最適化のポイント
- 求人情報をわかりやすく掲載(給与、勤務日数、勤務体系、福利厚生など)
- 写真や動画で職場の雰囲気を伝える(院内ツアー、医師やスタッフのインタビューなど)
- 「働くメリット」や「教育体制」などの独自性を明記
- スマートフォン対応・読みやすいレイアウトの導入も必須
特に、「応募前に不安を取り除く」ための情報を充実させることが、問い合わせ数や応募率アップに直結します。
5-2. SNSを活用した情報発信とブランディング
SNSは単なる情報発信ツールではなく、病院の“ブランド”を築く武器になります。InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどを通じて、病院の取り組みやスタッフの声、日常の様子を発信することで、求職者に「ここで働いてみたい」と思わせることができます。
■ SNS運用のコツ
- “堅すぎない”トーンで親近感を演出
- 採用情報だけでなく、医師の活躍、チーム医療、勉強会の風景なども投稿
- ハッシュタグ(#医師求人 #働きやすい病院 など)を活用して検索に強くする
SNSでの発信は、応募者との**最初の接点(ファーストコンタクト)**をつくる重要なツールです。
5-3. オンライン採用イベントの実施と効果
コロナ禍を機に普及したオンライン説明会・Web面談・バーチャル病院見学などは、今や地方病院にとっても都市圏から医師を集めるチャンスです。
■ オンライン採用のメリット
- 遠方からでも気軽に参加してもらえる
- 移動・日程調整が不要で医師の負担を軽減
- 見学前に病院の雰囲気を伝えられる
たとえば「Zoomで30分の院内説明会」や「医局向けWebセミナー」などを定期開催することで、情報収集段階の医師に接触する機会が増えます。
参加者からのリアルな質問を聞くことで、医師側の不安やニーズが見える化され、採用条件の改善にもつながります。

6. 公的支援制度と外部リソースの活用
採用難・人材不足という課題に対し、すべてを病院単体で解決しようとするのは非効率です。国や自治体による公的支援や、外部の専門機関を上手に活用することで、コストを抑えつつ、採用・定着の仕組みを強化することが可能になります。本章では、活用すべき代表的な支援策とリソースをご紹介します。
6-1. 医療介護総合確保基金の概要と活用方法
「医療介護総合確保基金」は、地域の医療提供体制を確保・強化することを目的に、都道府県に設置されている国の補助制度です。特に、人材育成や医療機関の機能分化、医師の偏在解消などの支援に活用されています。
■ 活用できる主な事業内容
- 医師・看護師の研修費用の補助
- 働き方改革に対応したICT導入の補助
- 地域医療を担う医師の確保・定着支援
- 医療機関の再編・統合のための事業支援
■ 利用のポイント
都道府県ごとに支援対象や申請期間が異なるため、定期的に自治体のWebサイトを確認することが重要です。補助対象となる機器導入や研修内容を見極めて、計画的に申請書類を準備しましょう。
6-2. 地域医療連携推進法人の活用によるリソース共有
「地域医療連携推進法人」とは、複数の医療機関が法人格をもって連携する仕組みで、地域全体で医療資源を効率的に活用するための枠組みです。
■ 活用のメリット
- 医師や看護師の相互派遣による業務負担の平準化
- 共同研修・教育体制によるスキルアップの共有
- 医療機器や人事・給与管理の共同利用によるコスト削減
- 法人全体でのブランディングや広報活動も可能
単独の病院では実現が難しい取り組みも、地域の医療機関同士で連携すれば効率よく対応できます。
医師が「病院間を行き来しながら働く」スタイルの導入も、柔軟な働き方の一例として注目されています。
6-3. 人材紹介サービスやコンサルティングの利用
人材確保において、医師専門の人材紹介会社や、医療業界に特化した採用コンサルティングサービスの活用も有効です。
■ 人材紹介サービスの特徴
- 勤務条件やスキル要件に応じた候補者のマッチング
- 非公開求人として、条件交渉や契約サポートも代行
- 採用が決定した時点で報酬が発生する「成功報酬型」が主流
■ コンサルティングの活用場面
- 採用ページや求人票の改善提案
- ブランディングやSNS戦略の構築支援
- 希望に合った医師のヘッドハンティング支援
- 医師とのコミュニケーション方法のアドバイス
特に採用活動に慣れていない病院では、第三者の視点で改善点を見つけてもらうことで、短期間で成果が出やすくなります。
医療現場における人材確保は、今や病院経営の最重要課題のひとつです。医師・看護師ともに有効求人倍率は高水準が続き、特に地方では深刻な人手不足に悩まされている病院も少なくありません。採用しても定着しない、応募がまったく来ない――そんな悩みを抱える医療機関も多いのではないでしょうか。
本記事では、人材不足の背景から、採用成功のための戦略、そして長く働き続けてもらうための職場づくりまで、実践的なノウハウを解説しました。医師にとって魅力的な条件とは何か。働き方改革にどう対応すべきか。職員の価値観やライフスタイルを尊重し、キャリアアップ支援やメンタルヘルス対策まで整えた環境こそが、選ばれる病院への第一歩となります。
さらに、採用活動の強化にはデジタルの力も不可欠です。ウェブサイトやSNSを活用した情報発信、オンライン採用イベントの実施などは、病院の魅力を広く伝える手段として有効です。また、公的支援制度や外部サービスを上手に使えば、コストを抑えつつ専門的なサポートを受けることも可能です。
弊社独自のヘッドハンティングも対応しておりますので、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
「医師が集まり、定着する病院」を目指して、できることから一歩ずつ始めてみませんか?