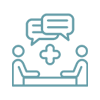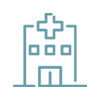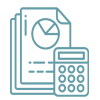「医療法人の買収に興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない」
「後継者が見つからず、このままでは病院をたたむしかないかもしれない」
こうした悩みを抱える医療経営者の方は、年々増えています。少子高齢化の進行や医師不足、経営環境の変化により、医療機関の継続にはこれまで以上に柔軟な選択肢と判断が求められる時代になりました。そのなかで注目を集めているのが、“医療法人の買収(M&A)”という選択肢です。
買収というと「ハードルが高い」「営利目的で良くない印象がある」といった先入観を持たれがちですが、実際には地域医療を守るための有効な手段であり、次世代への円滑な承継策でもあるのです。むしろ、医療法人買収は“攻め”というより“守り”の経営判断とも言えるでしょう。
この記事では、医療法人買収の基本知識から具体的なスキーム、手続きの流れ、注意点、そして買収後の人材確保や働き方改革、成功事例に至るまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説しています。
医療法人の将来を真剣に考えるあなたにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。経営の不安を希望に変えるヒントが、きっと見つかるはずです。
1. 医療法人買収の基礎知識
1-1. 医療法人買収とは何か
医療法人買収とは、第三者が既存の医療法人の経営権を引き継ぎ、病院やクリニックの運営を担う仕組みです。一般企業と異なり、医療法人は医療法に基づく特別な法人形態であり、その買収には一定の法的ルールと行政手続きが必要です。
近年では、後継者不在や経営悪化を背景に、M&A(合併・買収)による医療法人の承継ニーズが増加しています。また、医療機関に新たに参入したい法人にとっても、既存法人の買収は効率的な事業拡大手段となっています。
1-2. 医療法人の種類と特徴
医療法人には主に「社団医療法人」と「財団医療法人」の2種類がありますが、実務上は社団医療法人が大半を占めます。さらに、社団医療法人には「持分あり」と「持分なし」の法人があります。
- 持分あり医療法人:出資者(社員)が法人財産の持分を持ち、法人解散時にはその財産の分配を受けられます。2007年の法改正以降は新規設立できず、既存法人のみが該当します。
- 持分なし医療法人:出資者に持分がなく、財産の私的帰属はありません。公共性が高く、今後のM&Aではこちらが主流となります。
このように、買収を検討する際には、法人の種類によって法的手続きや譲渡方法が異なるため、事前に法人形態を把握しておくことが非常に重要です。
1-3. 買収のメリットとリスク
医療法人の買収には、大きなメリットがある一方で、特有のリスクも伴います。以下に代表的なものをまとめます。
■ 買収のメリット
- 既存の医療機能・設備・スタッフを活用できるため、新規開業よりも初期投資や準備期間を抑えられる。
- 地域での認知や信頼を引き継げるため、患者の流出リスクが低く、安定した経営が見込める。
- 行政からの許認可や指定の引き継ぎが可能な場合が多く、スムーズな運営開始が可能。
■ 買収のリスク
- **法人の負債や訴訟リスク、人材トラブルなどが“見えにくい”まま承継される可能性がある。
- 職員や患者との関係性が崩れると、評判の悪化や離職・流出が起きやすい。
- 医療法や税務・労務に関する高い専門性が求められるため、事前の調査と専門家の支援が不可欠。
つまり、買収は事業の近道である一方で、“相手をよく知ること”と“慎重な準備”が成功の鍵となります。

2. 医療法人買収の主なスキーム
医療法人の買収は、通常の企業買収とは異なり、医療法に基づく制約が多くあります。そのため、適切なスキーム(買収手法)を選ぶことが、円滑なM&Aの成功につながります。ここでは、医療法人で一般的に用いられる3つのスキームをご紹介します。
2-1. 出資持分譲渡
「出資持分譲渡」とは、持分あり医療法人の出資者(社員)が持分を第三者に譲渡することで、経営権を移転するスキームです。会社でいうところの株式譲渡に近いイメージです。
■ 特徴とポイント
- 【メリット】法人そのものを譲渡するため、許認可や施設・従業員の引き継ぎが比較的スムーズ。
- 【留意点】譲渡には社員総会での承認が必要な場合があり、内部調整が不可欠。
- 【リスク】持分の評価額により、多額の譲渡益課税(所得税や贈与税)が発生する可能性があります。
※現在は「持分なし医療法人」の設立が主流であり、将来的にこのスキームは限定的になる可能性もあるため、法改正動向にも注意が必要です。
2-2. 事業譲渡
「事業譲渡」とは、医療法人が運営しているクリニックや診療所などの“事業そのもの”を他法人へ譲渡する方法です。法人格の引き継ぎはなく、設備や人材、患者情報などを新たな法人へ移転する形になります。
■ 特徴とポイント
- 【メリット】買い手側が必要な資産・人材のみを選んで取得できるため、柔軟な対応が可能。
- 【留意点】施設の名義変更や新規許認可の取得など、行政手続きが複雑かつ煩雑。
- 【リスク】事業譲渡によって患者や職員に不安を与える場合があるため、事前の周知と丁寧な説明が重要。
事業譲渡は、クリニックなどの小規模医療機関の承継でよく用いられます。
2-3. 合併・吸収分割
「合併」や「吸収分割」は、複数の医療法人を1つに統合するスキームであり、主に規模の大きい法人やグループ経営で用いられます。
■ 合併の特徴
- 吸収合併:一方の法人が他方の法人を吸収し、すべての資産・負債・権利義務を承継。
- 新設合併:両法人を解散し、新法人を設立してすべてを移転する方式(稀)。
■ 吸収分割の特徴
- 特定の事業部門のみを切り出し、別法人に承継させる方法。
- 医療法人の機能再編や、グループ内再構築に適しています。
■ 留意点
- 合併・分割には都道府県知事の認可が必要であり、手続きに時間とコストがかかる。
- 法人の規模や方針によって、組織文化の統合やスタッフ間の調整にも注意が必要です。
医療法人の買収には、「持分譲渡」「事業譲渡」「合併・分割」といった複数のスキームが存在し、それぞれメリット・デメリットがあります。
どの手法を選ぶかは、法人の形態・規模・譲渡の目的・今後の運営方針によって最適解が異なります。
3. 医療法人買収の手続きと注意点
医療法人の買収は、一般企業のM&Aと比べて法的・制度的に複雑な側面があります。そのため、十分な準備と丁寧なプロセス管理が不可欠です。この章では、失敗を避けるために押さえておくべき基本的な手続きと注意点を3つのフェーズに分けてご紹介します。
3-1. デューデリジェンスの実施
「デューデリジェンス(DD)」とは、買収対象の法人が抱える財務・法務・人事・運営上のリスクを調査・洗い出しするプロセスです。買収後に「こんな問題があるとは思わなかった」と後悔しないためにも、極めて重要なステップです。
■ 主な調査項目
- 財務DD:貸借対照表や損益計算書のチェック、不良債権や未収金の有無
- 法務DD:許認可の有効性、訴訟リスク、契約書の整合性、コンプライアンス状況
- 人事DD:雇用契約、給与体系、社会保険、退職金制度、労務トラブルの有無
- 業務DD:患者数や診療実績、地域での評判、収益構造の把握
デューデリジェンスは、必ず医療分野に強い会計士・弁護士・M&Aアドバイザーのサポートを得て実施しましょう。
3-2. 契約書の作成と締結
デューデリジェンスでリスクを把握した後は、買収に関する正式な契約書を作成します。契約書は、後々のトラブルを避けるために、譲渡条件や引き継ぎ事項、責任の所在を明確に定める必要があります。
■ 契約書に盛り込むべき主な項目
- 譲渡金額と支払い方法(分割・一括など)
- 譲渡対象の明細(資産・事業・持分など)
- 表明保証(相手方の情報が正確であることの宣言)
- クロージング(引き渡し日)までの役割分担
- 表面化していない債務や訴訟リスクへの補償条項(インデムニティ)
契約書の作成には必ず医療法人に精通した弁護士の関与が必須です。テンプレートで済ませるのではなく、ケースごとにカスタマイズした契約が重要です。
3-3. 関係者への通知と調整
契約締結と並行して進めるべきなのが、関係者(職員・患者・関係機関)への丁寧な通知と調整です。特に医療法人では、突然の経営交代が現場や患者に不安を与えるリスクが高いため、慎重なコミュニケーションが求められます。
■ 関係者ごとの対応例
- 職員(医師・看護師・事務職):雇用条件や勤務体制の変更があるかを早めに共有し、安心感を持ってもらう
- 患者:診療体制や主治医が変わらないこと、もしくは変更がある場合の影響を丁寧に説明
- 行政・取引先:許認可や契約の名義変更、届出のタイミングに注意
円滑な承継には、“経営が変わっても中身は変わらない”という安心感をいかに周囲に伝えられるかが重要です。
医療法人買収では、「調査」「契約」「説明」の3ステップを丁寧に行うことが、トラブルを避けて成功するカギです。買収は単なる手続きではなく、“人”と“信頼”を引き継ぐデリケートなプロセスであることを忘れずに進めていきましょう。

4. 医療法人買収における人材確保のポイント
医療法人を買収しても、「人材」が確保・定着できなければ、安定した運営は望めません。特に医師・看護師などの医療職は、採用難・定着難が深刻な領域です。ここでは、買収後における人材確保の戦略的なポイントを3つに分けて解説します。
4-1. 医師・看護師の採用戦略
医療法人買収後、まず直面するのが現場の人員不足や医師の確保です。買収時には在籍していたスタッフが退職する可能性もあるため、「戦力となる人材をいかに早く・確実に採用するか」が重要です。
■ 採用戦略のポイント
- 条件だけでなく“理念や方針”を明示する:求職者は報酬だけでなく、「どういう医療を目指しているか」を重視します。
- 医療系専門の人材紹介会社との連携:ニーズに合う人材を効率的に探せます。
- 柔軟な勤務条件の提示:週3勤務や当直なしなど、働き方の選択肢があることで応募が増える傾向にあります。
買収直後の採用活動では、「何が変わって、何が変わらないのか」を明確に伝えることで、不安を減らし応募につなげることができます。
4-2. 労働環境の整備と働き方改革
人が集まり、長く働いてもらうためには、“働きやすさ”の整備が最優先です。特に医師については、2024年から始まった時間外労働の上限規制への対応が求められています。
■ 整備すべき労働環境の要素
- タスクシフト:医師の事務負担を医療クラークや事務職が担うことで、診療に集中できる体制に。
- 勤務シフトの柔軟性:当直や休日勤務の負担をチームで分担し、過労を防止。
- 休暇の取得推進と代替スタッフの配置:リフレッシュの機会を確保し、バーンアウトを予防。
また、最新の電子カルテや予約システムの導入など、ITを活用した効率化も労働負担軽減につながります。
4-3. 人材定着のための組織戦略
採用しても、辞められてしまっては意味がありません。人材の定着には、組織としての“信頼”と“育成環境”が整っていることがカギとなります。
■ 定着に効く取り組み例
- 明確なキャリアパスの提示:将来どう成長できるかを示すことで、長期的なモチベーションに。
- 定期的なフィードバック・評価制度:適切に評価される環境は、やりがいと公平性を実感させます。
- メンタルヘルスと職場コミュニケーションの支援:気軽に相談できる風土づくりが、離職防止に直結。
また、買収直後は「経営が変わることで職場がどうなるか」という不安が強まります。安心して働ける職場文化の醸成が、定着への第一歩です。
医療法人買収の成功には、「数字の引き継ぎ」だけでなく、「人の引き継ぎと新たな関係構築」が欠かせません。採用→環境整備→定着というサイクルを整えることで、買収後の病院・クリニックは“再スタート”ではなく“進化”するステージへと進むことができます。
5. 成功事例から学ぶ医療法人買収
医療法人の買収には多くの不安やハードルが伴いますが、正しく準備し、的確な施策を講じれば、買収後に大きな成果を上げることも可能です。この章では、実際に成果を上げた3つの成功事例をご紹介します。
5-1. 地域密着型病院の買収成功事例
ある地方都市の中規模病院では、理事長の高齢化により事業承継が必要となり、地元企業グループによる医療法人買収が実施されました。
■ 成功のポイント
- 地域ニーズの継続的なリサーチにより、買収後も「地元のかかりつけ病院」としての信頼を維持。
- 従業員の雇用・待遇を変更せず引き継ぐ方針を明確化し、スタッフの離職を防止。
- 地元行政や医師会との事前協議を通じて、地域からの理解と協力を獲得。
結果として、買収後も患者数は減ることなく、むしろ**「経営が安定した」「診療体制が拡充した」といった評価が高まり、病床稼働率も上昇**しました。
5-2. デジタル施策で成果を上げた事例
首都圏の診療所を買収したケースでは、新オーナーがIT・デジタル施策を積極的に導入し、業務効率と集患力の両方を向上させました。
■ 実施した取り組み
- 電子カルテとクラウド型レセプトシステムを導入し、診療後の事務作業時間を40%削減。
- ウェブ予約・LINE予約システムの導入により、患者の利便性を向上。
- SEO対策を施した採用・診療案内ページのリニューアルで、月間アクセス数が2倍以上に。
これらの施策により、患者数が前年比20%増、スタッフ採用の問い合わせも大幅に増加。買収を機に“アップデートされた医院”として新しいブランド価値を創出しました。
5-3. 人材確保による経営安定化事例
都市郊外の老舗クリニックを買収した企業は、人材不足で赤字寸前だった経営を再建。採用と定着の強化に注力し、収益改善を実現しました。
■ 実施した施策
- 医療系人材紹介会社との連携を強化し、医師・看護師の採用活動を外注化。
- 働き方改革を徹底し、「週4日勤務・当直なし」など柔軟な勤務形態を用意。
- 定着率向上のため、メンタルヘルス支援制度と定期フィードバック制度を導入。
買収から1年後、正職員の離職率が半減し、診療体制の安定化に成功。黒字転換だけでなく、「働きやすい職場」として医師・スタッフの紹介も増え、好循環が生まれています。
医療法人買収は、単なる“事業の引き継ぎ”ではなく、地域・スタッフ・患者との関係性を再構築し、新たな価値を生み出すプロジェクトです。成功事例から学べるのは、以下の3点です:
- 現場の不安を抑える“丁寧な関係構築”
- テクノロジーを活かした“業務革新”
- 人材戦略を中心に据えた“働き方改革”

6. 専門家の活用と支援体制
医療法人の買収は、医療法・税務・労務・許認可といった複雑な領域が絡むため、「専門家の力を借りる」ことが成功の近道です。また、近年では公的支援や金融機関による後押しも充実しており、それらをうまく組み合わせることでリスクを抑え、スムーズな承継が可能になります。
6-1. コンサルタントやアドバイザーの選び方
医療M&Aにおいて最も重要なパートナーの一つが、医療法人の買収に精通した専門コンサルタントやアドバイザーです。
■ 選び方のポイント
- 医療法や診療報酬制度への理解があること(一般的なM&A専門家とは異なる)
- 医療機関での買収・承継の実績があること
- 医師や従業員とのコミュニケーション支援もできること
さらに、単なるアドバイスだけでなく、買収スキームの設計から手続き、デューデリジェンスの実行、関係者調整まで一貫してサポートできる体制かどうかも重要です。
6-2. 金融機関や専門機関の支援策
医療法人買収には数千万円〜数億円単位の資金が必要になるケースもあるため、金融機関との連携は不可欠です。
■ 活用すべき支援例
- 日本政策金融公庫:後継者承継資金、M&A支援資金などの低利融資制度
- 地域の信用金庫・地方銀行:地元医療法人との関係性を活かした承継案件紹介
- 医療系専門ファンド:民間の医療特化型投資会社が買収をサポートする事例も増加
また、地域医師会や医療系財団などが設ける承継マッチング制度に参加すれば、買収先の紹介や、行政との調整支援も受けられるケースがあります。
6-3. 公的支援制度の活用方法
国や自治体も、医療法人の承継・再編を後押しするさまざまな制度を用意しています。うまく活用することで、費用負担を軽減しながら、安心して買収を進めることが可能です。
■ 代表的な制度例
- 中小企業庁「事業承継・引継ぎ補助金」:買収関連費用(専門家費用・システム導入など)を補助
- 厚生労働省「医療介護総合確保基金」:医療提供体制の再編・確保を目的とした補助金(都道府県経由)
- 事業承継・引継ぎ支援センター:公的M&Aマッチングや専門家派遣を無料で実施
これらの制度は、タイミングや要件を満たす必要があるため、早期の情報収集と計画的な申請準備が鍵となります。
医療法人買収は、専門的な知識と実務経験が必要なプロジェクトです。信頼できる専門家の力を借り、金融・行政の支援を活用することで、リスクを抑えつつ、最短ルートでの承継が実現できます。
「自分たちだけで進める」よりも、「信頼できる外部と進める」ことが、買収成功の第一歩です。
医療法人の買収は、病院やクリニックの将来を左右する重要な選択です。少子高齢化や後継者不在によって、多くの医療機関が事業承継を必要としている一方で、買収側にも高い専門性と準備が求められます。
本記事では、医療法人買収の基本知識から、買収手法(スキーム)、手続きの流れ、注意点、そして買収後の人材確保・定着戦略までを体系的に解説しました。成功事例を見ても明らかな通り、ポイントは「人材の確保と働きやすい職場づくり」、そして「患者や地域との信頼関係の維持」です。
また、買収を成功させるには、自力での判断だけでなく、医療法に精通したコンサルタントや金融機関、公的支援制度の活用が不可欠です。特に初めて医療M&Aに取り組む方は、専門家と連携しながらリスクを最小限に抑えることが重要です。
医療法人買収は、単なる経営権の移転ではなく、医療の質と地域貢献を次世代へつなぐ“医療のバトンリレー”とも言えるもの。だからこそ、確かな準備と信頼あるパートナー選びが成功の鍵を握ります。