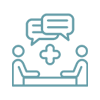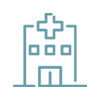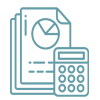「そろそろクリニックを手放そうか」と考え始めたとき、多くの院長先生が最初に直面するのが「売却の相場はどれくらいなのか?」「どんな流れで手続きを進めるのか?」という疑問です。少子高齢化や医療ニーズの変化、後継者不足などの影響もあり、近年はクリニックを売却して事業を承継させるケースが増加しています。特にM&A市場の活発化に伴い、都市部だけでなく地方でもクリニックの売却事例が広がっており、選択肢として検討する経営者が増えています。
しかし、いざ売却を検討すると「いくらで売れるのか」「スタッフや患者にどう説明すべきか」「税務・法務上の注意点は?」など、不安や悩みは尽きません。売却は単なる取引ではなく、これまで築いてきた地域医療の信頼やスタッフの雇用を守る重要なプロセスです。そのため、正しい知識と準備をもって臨むことが成功のカギとなります。
本記事では、クリニック売却の基礎知識から価格評価の方法、売却スキームの違い、実際の手続きの流れ、税務・法務の注意点、そして売却を成功に導くための具体的なポイントまでを徹底解説します。これから売却を検討する方はもちろん、将来的に選択肢として考えている方にとっても役立つ内容となっています。ぜひ最後までご覧いただき、安心して次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
1.クリニック売却(譲渡)の意義と現状
1-1. なぜクリニック売却が選ばれるか
クリニックの売却は、単に「経営から退く」ためだけの手段ではありません。院長自身の引退や体力的な限界に伴う選択はもちろんのこと、経営資源の整理や、より大きな医療法人グループへの参加による経営基盤の強化といった前向きな戦略としても活用されています。
また、売却を通じて地域の患者やスタッフの受け皿を確保できる点も重要です。閉院を選択すれば診療の継続が途絶えますが、売却であれば患者の通院先やスタッフの雇用を守ることが可能です。結果的に、医療サービスの持続性を確保する社会的意義も大きいのです。
1-2. 売却件数・M&A市場の動向
近年、クリニックや中小規模医療法人の売却件数は右肩上がりに増加しています。背景には、後継者不足や経営環境の変化に加え、M&A仲介市場の拡大があります。かつては「医療機関の売却=珍しいケース」と思われていましたが、現在では都市部だけでなく地方でも一般的な選択肢となりつつあります。
特に、医療M&Aに特化した仲介会社やプラットフォームの登場により、売り手・買い手双方のマッチングが容易になったことも追い風となっています。こうした市場の成熟によって、**「適正価格での売却」や「スムーズな承継」**が実現しやすくなってきました。
1-3. 後継者不在問題と売却の関係
クリニック売却が増加している最大の理由のひとつが「後継者不在」です。医師の高齢化が進み、子ども世代が医業を継がないケースも増えているため、閉院か売却かの選択を迫られる院長が増えています。
このとき売却を選ぶことで、地域医療の継続性を守ることができます。例えば、スタッフが働き続けられる環境を確保できたり、患者も安心して通院を続けられたりと、経営者個人の事情と地域社会のニーズを両立させることが可能です。
クリニック売却は「経営者のリタイア手段」というイメージを超え、経営の選択肢のひとつとして一般化しています。市場環境の変化や後継者問題を背景に、今後も売却件数は増加する見込みです。重要なのは、「いつ・どのように」売却するかを早めに検討し、適切な準備を整えることです。
2. 売却価格・相場・評価方法
2-1. 個人クリニックと医療法人の相場比較
クリニックの売却価格は、形態によって大きく異なります。
- 個人クリニックの場合:数百万円〜数千万円程度が一般的。主に設備や営業権(のれん代)、患者基盤が評価対象となります。
- 医療法人クリニックの場合:規模が大きく、法人格があるため数千万円〜数億円になることも。法人としての信用、複数診療科や分院の有無が価格に大きく影響します。
相場はあくまで目安であり、立地条件・診療科目・過去の収益実績によって大きく変動するのが特徴です。
2-2. 価格評価の3つの主要手法
クリニック売却では、以下の3つの評価手法が用いられることが多いです。
- 純資産法
資産から負債を差し引いた「純資産」を基準に算定。設備や不動産が多いクリニックで有効。 - 営業権法(のれん代評価)
過去の利益実績や患者基盤を評価し、将来の収益力を反映。都市部や人気診療科のクリニックで高く評価されやすい。 - DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)
将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて算出。精緻な分析が可能で、大規模な医療法人や投資型買収で活用されやすい。
2-3. 価格を左右する要因
売却価格は単なる収益性だけでなく、複合的な要因に影響されます。
- 立地条件:駅近や人口密集地は高評価。地方でも競合が少ない場合は評価アップ。
- 診療科目:需要の高い内科や整形外科は安定性が高く、相場が上がりやすい。
- 患者数とリピート率:継続的な患者基盤があるかどうかは、営業権評価に直結。
- スタッフの継続性:経験豊富なスタッフが残る前提なら、引き継ぎリスクが低下。
- ブランディング力:地域での知名度や口コミ評価も無視できないポイント。
クリニックの売却価格は、「数字で見える資産」だけでなく、「患者との信頼関係」「スタッフ体制」「地域でのブランド」といった無形資産の評価も大きな要素となります。売却を有利に進めるには、事前に経営数値の改善や体制整備を行い、評価を高めておくことが効果的です。

3. 売却スキームと譲渡方法の選択肢
3-1. 事業譲渡/資産譲渡/持分譲渡の違い
クリニックの売却にはいくつかのスキームが存在します。その代表的なものが事業譲渡・資産譲渡・持分譲渡です。
- 事業譲渡:診療科や患者基盤、スタッフ、設備など「事業そのもの」を譲渡する方法。個人開業医が選択することが多く、柔軟性が高いのが特徴です。
- 資産譲渡:建物、医療機器、不動産といった個別の資産を売却する方法。買い手側が必要な資産だけを取得できるメリットがあります。
- 持分譲渡:医療法人の場合、出資持分や株式を譲渡する方法。法人そのものを引き継ぐため、契約関係や許認可の継続性が確保されやすいのが強みです。
3-2. 吸収分割・合併・分割等も含めた選択肢
規模の大きい医療法人では、M&Aのスキームとして吸収分割や合併が選ばれるケースもあります。
- 吸収分割:クリニックの一部事業を他の法人に承継させる方式。不要な部門を切り離し、必要な部門だけを引き継げます。
- 合併:複数の医療法人が一体化する方法で、経営資源の統合によるスケールメリットを得られるのが利点です。
- 会社分割:複数事業を持つ大規模法人が一部を切り出す形で承継する方法。医療法人の分院運営などに使われることがあります。
3-3. スキームごとのメリット・注意点
それぞれのスキームにはメリットと注意点があります。
- 事業譲渡:柔軟だが、契約の再締結が必要なため事務負担が大きい。
- 資産譲渡:必要な資産だけ承継できるが、患者やスタッフの引き継ぎに課題が残ることも。
- 持分譲渡:法人を丸ごと引き継ぐためスムーズだが、過去の債務やリスクも一緒に承継する点に注意。
- 合併・分割:スケールメリットを得られる一方、組織文化や経営方針の違いが摩擦を生むことがある。
クリニック売却では「どのスキームを選ぶか」が成功の分かれ目になります。売り手側の目的(引退・資金化・継続支援)と、買い手側のニーズ(規模拡大・地域進出・人材確保)を整理したうえで、最適な方法を選択することが重要です。
4. 売却の流れと実務手続き
4-1. 売却意向の決定と戦略検討
最初のステップは「本当に売却するのか」を明確にすることです。引退や後継者不在など理由はさまざまですが、売却の目的を整理することで、その後の手続きや交渉方針が決まります。
- 「地域医療の継続を重視したい」
- 「できるだけ高く売却したい」
- 「スタッフの雇用を守りたい」
といった優先順位を明確にすることが大切です。
4-2. 仲介業者・FA(ファイナンシャルアドバイザー)の選定と契約
クリニック売却は専門的な知識が必要なため、M&A仲介会社やFAのサポートを受けるのが一般的です。
- 医療分野に強い仲介業者かどうか
- 過去の実績や成功事例の有無
- 費用体系(着手金・成功報酬など)の透明性
これらを比較し、自院に合ったパートナーを選ぶことが成功の第一歩です。
4-3. 価値評価(デューデリジェンス準備)
買い手候補が見つかると、**デューデリジェンス(精査)**が行われます。
- 財務資料(決算書、収支報告)
- 人事資料(スタッフ数、雇用契約)
- 設備や医療機器の資産情報
- 患者数や診療実績のデータ
これらを事前に整理しておくと、評価がスムーズに進み、価格交渉でも有利になります。
4-4. 基本合意・最終契約・クロージング
条件がまとまったら、基本合意書を締結します。その後、最終的な契約内容を詰め、最終契約書の署名・捺印を経てクロージング(取引完了)となります。
この段階では、買い手との細かい条件調整(売却価格の確定、引き継ぎ条件、スタッフ処遇)が行われるため、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが求められます。
クリニック売却の流れは大きく「意向決定 → 仲介選び → 価値評価 → 契約締結」の4ステップです。事前準備の質が交渉力や売却価格を左右するため、早めに準備を始めることが成功のカギとなります。

5. 必要書類・データ準備と引き継ぎ体制
5-1. 財務・会計書類・決算資料
クリニック売却にあたって最も重視されるのが財務データです。
- 過去3〜5年分の決算書
- 損益計算書・貸借対照表
- 月次の収支資料
これらは買い手が収益性やリスクを判断する基礎資料となります。数字が整理されていないと評価が下がるため、早めに会計士と連携して整えておくことが大切です。
5-2. 設備・医療機器・不動産関連書類
クリニックに備え付けられた医療機器や建物、不動産は、売却価格に直結する重要な資産です。
- 医療機器の購入時期・型番・稼働状況
- 建物や土地の権利証、賃貸借契約書
- リース契約や保守契約の有無
これらをリスト化して提示できるように準備しておくと、スムーズな評価と引き継ぎが可能になります。
5-3. 人事・雇用契約・スタッフ情報
スタッフの雇用継続は、買い手にとっても大きな関心事です。
- 職員数・職種・雇用形態
- 個別の雇用契約書や就業規則
- 勤務年数や給与テーブル
こうした情報が整備されていれば、買い手は人材の引き継ぎリスクを低く見積もり、売却交渉も進みやすくなります。
5-4. 診療実績・患者数・マーケティングデータ
患者基盤はクリニックの「のれん代」に直結します。
- 直近数年の患者数推移
- 診療科ごとの収益構成
- リピート率や紹介率
- ホームページや口コミの評価状況
これらを整理することで、「安定的な患者基盤を持つクリニック」として高く評価されやすくなります。
クリニック売却を円滑に進めるには、財務・設備・人事・患者基盤の4つのデータを整備しておくことが不可欠です。資料が揃っているほど買い手の安心感は増し、結果として売却価格や条件交渉に有利になります。
6. 税務・法務上の注意点
6-1. 譲渡所得税・法人税・消費税の取り扱い
クリニック売却において、最も注意が必要なのが税金の問題です。
- 個人開業医の場合:売却益は「譲渡所得」として課税対象になります。特に不動産を含む場合、税率や特例の適用が変わるため事前確認が必須です。
- 医療法人の場合:法人としての譲渡益は法人税課税の対象となり、利益計上のタイミングも考慮が必要です。
- 資産譲渡のケース:医療機器や建物の譲渡には消費税がかかる場合があるため、契約前に税務上の扱いを整理しておくことが重要です。
6-2. 医療法・許認可・事業承継規制の継承
クリニックは医療法に基づく厳格な規制があり、売却に伴う許認可の承継は慎重に行わなければなりません。
- 個人クリニック:開設者が変わるため、新たな開設許可の取得が必要。
- 医療法人:持分譲渡であれば法人自体は存続するため、許認可の継続が比較的スムーズ。ただし理事長の変更手続きが必要となる場合があります。
また、診療科目や診療所の構造・設備が規制を満たしているかどうかも改めて確認されるため、法務リスクを洗い出しておくことが大切です。
6-3. 契約や債務の引き継ぎ
売却時には、既存の契約や債務も引き継がれることがあります。
- リース契約や賃貸借契約:契約の名義変更が必要。場合によっては大家やリース会社の承諾が求められます。
- 借入金や保証債務:買い手に引き継がれるケースと、売り手側で清算するケースがあり、契約内容によって大きく変わります。
- 取引先との契約:医薬品や医療材料の供給契約などは、承継の可否を確認しておく必要があります。
税務と法務の問題は、売却価格と同じくらい重要です。思わぬ課税負担や法的トラブルを避けるためにも、税理士・弁護士など専門家と早めに相談しながら進めることが、クリニック売却成功の大きなポイントとなります。

7. 売却成功のポイントとリスク回避策
7-1. クリニック価値を引き上げる事前改善施策
売却を検討する際は、少なくとも1〜2年前から準備を始めるのが理想です。
- 財務体質を健全化し、黒字化を維持する
- 不要な資産や赤字部門を整理してスリム化
- 診療実績や患者数を安定させる
これらを行うことで買い手の評価が高まり、売却価格を引き上げることが可能です。
7-2. 患者・スタッフを巻き込むコミュニケーション戦略
売却が決まった際に最も気を使うべきなのが、患者とスタッフへの対応です。
- スタッフには、雇用条件の継続を丁寧に説明する
- 患者には、診療体制が変わらず継続されることを伝える
不安を最小限に抑えることで、売却後の混乱を防ぎ、スムーズな承継につながります。
7-3. 交渉力・買い手選定のコツ
買い手は必ずしも「高値を提示した相手」が最適とは限りません。
- 経営方針や理念が近いかどうか
- 地域医療に対する理解や意欲があるか
- スタッフ・患者を大切にする姿勢があるか
こうした要素を重視することで、売却後の安定経営と地域医療の継続が期待できます。
7-4. 売却後も安定運営が可能な体制設計
売却はゴールではなく、スタートでもあります。引き継ぎ後も経営が安定するように、
- 数カ月間は院長が顧問的に残り、患者やスタッフをサポートする
- 運営マニュアルや診療ノウハウを文書化する
- 継続的にコミュニケーションが取れる体制を整える
こうした工夫が、売却後の信頼関係維持と混乱回避につながります。
クリニック売却を成功させるカギは、価格だけでなく、地域医療の継続・スタッフと患者の安心・買い手との相性にあります。事前の改善施策と周到な準備、そして信頼できるパートナーとの連携によって、納得感のある売却を実現することができます。
まとめ
クリニック売却は、院長のリタイアや後継者不在といった個人的な事情だけでなく、地域医療の継続やスタッフの雇用維持という社会的な意義を持っています。近年はM&A市場の成熟によって、売却は特別なものではなく、医療経営の「ひとつの選択肢」として広く認知されるようになってきました。
売却を成功させるためには、相場の把握やスキームの選択、必要書類の整備、税務・法務の確認といった入念な準備が欠かせません。さらに、売却価格だけに目を向けるのではなく、患者やスタッフが安心して診療を継続できるようにすることが最も重要なポイントです。
また、早めに準備を始め、専門家のサポートを受けながら進めることで、交渉力が高まり、納得のいく条件での売却が実現しやすくなります。財務改善や組織体制の整備など、日頃からの取り組みが「売れるクリニック」の条件をつくるのです。
クリニック売却はゴールではなく、新たな医療の継続に向けたスタートラインです。未来の地域医療を託すためにも、適切な知識と戦略を持ち、納得のいく承継を実現しましょう。